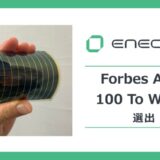資金調達データ
- 関連ワードコストダウン, 卸電力市場, 脱炭素, 自家発電設備, 資金調達
- 配信日2025年9月5日 10時00分
資金調達の概要
株式会社Flying Duckは、卸電力市場を活用した自家発電設備等の運用最適化システムに対する資金調達を実施し、1億円超の資金を集めました。この資金は主に人材の確保や、システムの開発・改良に充てられる予定です。Flying Duckは、脱炭素社会の実現を目指し、大規模工場向けにエネルギーの効率的な利用を促進するサービスを展開しています。特に、AI技術を駆使した数理最適化により、電力市場の需給に応じた最適なエネルギー運用を実現しています。この資金調達は、急速に変化するエネルギー市場において、顧客からの期待に応えるための重要なステップとされています。
さらに、資金の調達を可能にした背景には、Flying Duckが提供するサービスの需要の高まりがあります。大規模製造業において、コストの削減と同時に脱炭素を実現するシステムは、特に環境への配慮が求められる現代において大きな価値を持っています。これにより、企業経営者や財務担当者にとって、Flying Duckのサービスは非常に魅力的な選択肢となっています。
資金調達の背景(推測)
Flying Duckの資金調達の背景には、脱炭素社会の実現に向けた政府や企業の取り組みが影響を与えていると考えられます。近年、地球温暖化対策として温室効果ガスの排出削減が求められ、再生可能エネルギーの利用が促進されています。このような社会的な潮流から、特に大規模工場はエネルギー効率の改善と脱炭素化が急務となっています。そのため、エネルギーの運用最適化に特化したFlying Duckが提供するソリューションへの関心が高まっているのです。
また、卸電力市場の活性化も資金調達を後押しする要因でしょう。電力需給が変動する中で、再エネ電源の出力が増える時間帯に電力を効果的に使用するための技術が求められています。Flying Duckはこのシステムを通じて、電力コストの削減や環境負荷の低減に成功した実績を持つため、投資者からの信頼を得やすくなっています。
さらには、Flying Duckを支援した日本政策金融公庫や地域の信用金庫といった金融機関が、脱炭素化への取り組みを強化していることも考えられます。彼らにとって、持続可能なビジネスモデルに投資することは、社会的責任の観点からも重要です。このような背景が、Flying Duckの資金調達における強みとなりました。
資金調達が成功した理由(推測)
Flying Duckの資金調達が成功した理由として、いくつかの要素が考えられます。まず第一に、事業モデルの明確さです。Flying Duckは、脱炭素とコスト削減を両立させるという明確なミッションを掲げています。これは、企業の社会的責任が高まる中で、投資家やパートナーにとって非常に魅力的な要素となります。
次に、技術的な優位性が挙げられます。社長である八木賢治郎氏が博士号を持ち、数理最適化を用いて電力市場の効率的な活用方法を模索してきたことは、専門知識の裏付けとなっており、投資家から信頼を得る要因となったでしょう。その結果、事業の持続可能性や成長性に対する期待感が高まり、資金調達が成功したのだと推測されます。
また、Flying Duckはすでに特種東海製紙という大手企業と提携し、実績を出していることも成功の要因です。このような信頼性の高いパートナーとの協業は、投資家に対し「実現可能性」のメッセージを強く送ります。更に、複数の金融機関からの支援を受けていることは、事業に対する広範な社会的支持を示すものであり、資金調達の成功につながったと考えられます。
このように、解決すべき社会課題や明確なビジョンを持つこと、自社の強みを利用し、信頼性の高いパートナーとの関係を築くことが資金調達の成功に寄与した要因であると推測されます。
資金調達の参考にすべきポイント
Flying Duckの資金調達から得られる教訓として、いくつかのポイントが挙げられます。まず、事業モデルの社会的意義を重視することが重要です。現在の市場は、社会課題解決に向けた取り組みを求めています。従って、自社の事業が社会にどのような価値を提供するのかを明確にし、投資家や顧客に伝える努力が必要です。
次に、技術力の高さとその具体的な応用例を示すことです。特に、数理最適化やAI技術の活用は、競争優位性を生む要素となります。技術的な背景や実績を語ることで、投資家に対する説得力が増すでしょう。
さらに、信頼できるパートナーとの連携も重要です。大手企業や公的機関との協業は、資金調達における信頼性を高めます。提携先が持つブランドや実績は、投資家からの信頼を獲得する上で大きな力になります。
最後に、資金がどのように使われるのか、具体的なプランを示すことが求められます。資金調達後の活用計画を明確にし、それに基づいたスケジュールを示すことで、投資家に安心感を与えることができます。
これらのポイントは、法人経営者や財務担当者にとって、今後の資金調達活動に対して非常に重要な要素となるでしょう。実績を示し、透明性を持ったプランを展開することで、信頼を得ることが資金調達の成功につながります。
卸電力市場を活用して自家発電設備等の運用を最適化するシステムを提供、大規模製造業における大幅コストダウンと脱炭素の両立をサポートする「Flying Duck」、1億円超の資金調達を実施しました。株式会社Flying Duck(読み:フライングダック、以下「Flying Duck」)は、1億円超の資金調達を実施しました。これを元に採用・組織拡大及び、既存システムの改良・高度化を進めます。株式会社Flying Duck2025年9月5日 10時00分0
会社概要・サービス概要
Flying Duckは、脱炭素社会の実現を目指し、大規模工場などに向けて新しいエネルギーの使い方を提案する会社です。
今まで、エネルギー・電力を大量に消費する工場などでは、24時間安定的にエネルギーを消費して安定的に生産を行うこと、また、構内に保有する自家発電設備(電気と熱エネルギーを同時につくるコージェネレーションという形態を取ることが多い)も24時間安定的に一定運転することが常識でした。
脱炭素社会に向けては、太陽光や風力など再生可能エネルギー電源の拡大が重要ですが、これらは天候によって出力が大きく変動します。そこで、再エネ電源の出力が多い時間帯にそれらを多く使用し、逆に出力が少ない時間帯には電気を使わない、または保有する発電機があればそれらを運転して電気を送る、というように、再エネ電源の出力状況に応じてエネルギーの使い方にメリハリを付けていくことが重要になります。
さらに、東日本大震災を契機とした電力システム改革によって「卸電力市場」というものが活性化しています。この市場では、再エネ電源の出力が需要に対して過剰になる時間帯には0.01円/kWhという「ほぼタダ」の価格となり(さらに海外では「マイナス価格」というものもあり国内でも議論が進んでいます)、逆
出典 PR TIMES